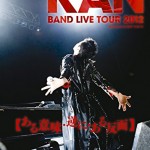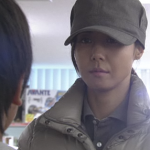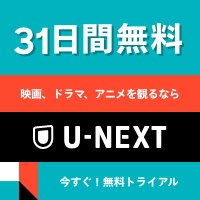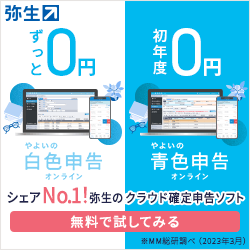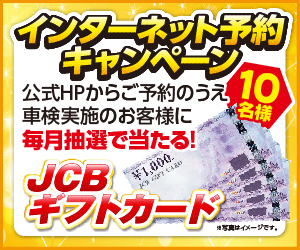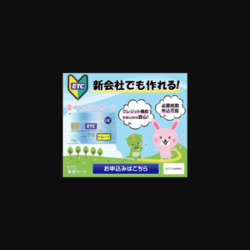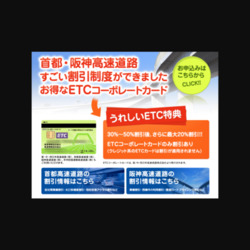最初は、福島、宮城、岩手の沿岸の町を回り、そこでくり広げられる惨劇を目撃することになった。幼いわが子の遺体を抱きしてめて棒立ちになっている二十代の母親、海辺でちぎれた腕
を見つけて「ここに手があります!」と叫んでいるお年寄り、流された車の中に親の遺体を見つけて必死になってドアをこじ開けようとしている若い男性、傾いた松の木の枝にぶら下がっ
た母親の亡骸を見つけた小学生ぐらいの少年……目に飛び込んでくるものは、怖気をふるいたくなるような死に関する光景ばかりだった。
(中略)
復興とは家庭や道路や防波堤を修復して済む話ではない。人間がそこで起きた悲劇を受け入れ、それを一生涯十字架のように背負って生きていく決意を固めてはじめて進むものなのだ。
(取材を終えて)
作品、と呼ぶにはあまりに惨い、現実を出来るだけ感傷にならないように記した、それでいて読みやすくまとめた(主題は、もちろん胸が苦しくなるほど読みづらいこと)本。
震災直後から現地に入り、現実がまだ把握出来ない状況で取材に応じた人たちの姿が客観的に描かれている。
それゆえ、地元の人たちには反発もあったという。
映画化にあたり、「なにが『遺体』だ。」と。
その気持ち、わかる。
お前らが感動するために、こんな被害を背負ってるわけじゃないんだと。
お前らの娯楽のために、ポップコーン食べながら、時間つぶしに、お手軽な感動のために、きれいな映画館でオシャレして、そんなためにわが家族は死んだんじゃないぞ、と。
「死体」と区別するための「遺体」なんて言葉、なんの意味があるんだろう。
かく言う私も、震災から10日あまりしたころ、被災地に行った。
そこかしこに「遺体安置所」と書かれた看板があり、さすがに興味本位で行くわけにはいかなかった(そんな興味、露ほどもわかなかったが)。
これ(映画化されたこの作品)を、「映画なんだから、それはそれ、これはこれでしょ」と、割り切ることが出来るだろうか。
「遺族にこそ見て欲しい」と、あなたならこれ、胸張って言えますか。
冗談じゃない。
映画じたいは、スタッフ含め現場の人たちの、製作中の心労がしのばれる。
苦しい。
西田敏行さんと志田未来さんの演技で、涙が出る。
いくらかの割合で、演技ではなかったろう。
なぜこの芝居をしなければならないのか、にもずいぶん悩まれたろう。
ひょっとして、依頼を引き受けたことにも。
それとは別に、「映画なんだから」と割り切る人らに、どうしても納得できない。
そういう、割り切れない気持ちが残る。
これを読み、映画を観ながら、
「これとおなじことが、たくさんの町で同時に起こっていたのだ」
という現実を考えると、現在の復興の遅れ方には憤懣やるかたない。
復興資金が使われず余っている(という言い方はおかしいが)というのも、なんとかなるだろうちょっと貸してみろ、と言いたくなる。
最初は、福島、宮城、岩手の沿岸の町を回り、そこでくり広げられる惨劇を目撃することになった。幼いわが子の遺体を抱きしてめて棒立ちになっている二十代の母親、海辺でちぎれた腕
を見つけて「ここに手があります!」と叫んでいるお年寄り、流された車の中に親の遺体を見つけて必死になってドアをこじ開けようとしている若い男性、傾いた松の木の枝にぶら下がっ
た母親の亡骸を見つけた小学生ぐらいの少年……目に飛び込んでくるものは、怖気をふるいたくなるような死に関する光景ばかりだった。
(中略)
復興とは家庭や道路や防波堤を修復して済む話ではない。人間がそこで起きた悲劇を受け入れ、それを一生涯十字架のように背負って生きていく決意を固めてはじめて進むものなのだ。
(取材を終えて)
作品、と呼ぶにはあまりに惨い、現実を出来るだけ感傷にならないように記した、それでいて読みやすくまとめた(主題は、もちろん胸が苦しくなるほど読みづらいこと)本。
震災直後から現地に入り、現実がまだ把握出来ない状況で取材に応じた人たちの姿が客観的に描かれている。
それゆえ、地元の人たちには反発もあったという。
映画化にあたり、「なにが『遺体』だ。」と。
その気持ち、わかる。
お前らが感動するために、こんな被害を背負ってるわけじゃないんだと。
お前らの娯楽のために、ポップコーン食べながら、時間つぶしに、お手軽な感動のために、きれいな映画館でオシャレして、そんなためにわが家族は死んだんじゃないぞ、と。
「死体」と区別するための「遺体」なんて言葉、なんの意味があるんだろう。
かく言う私も、震災から10日あまりしたころ、被災地に行った。
そこかしこに「遺体安置所」と書かれた看板があり、さすがに興味本位で行くわけにはいかなかった(そんな興味、露ほどもわかなかったが)。
これ(映画化されたこの作品)を、「映画なんだから、それはそれ、これはこれでしょ」と、割り切ることが出来るだろうか。
「遺族にこそ見て欲しい」と、あなたならこれ、胸張って言えますか。
冗談じゃない。
映画じたいは、スタッフ含め現場の人たちの、製作中の心労がしのばれる。
苦しい。
西田敏行さんと志田未来さんの演技で、涙が出る。
いくらかの割合で、演技ではなかったろう。
なぜこの芝居をしなければならないのか、にもずいぶん悩まれたろう。
ひょっとして、依頼を引き受けたことにも。
それとは別に、「映画なんだから」と割り切る人らに、どうしても納得できない。
そういう、割り切れない気持ちが残る。
これを読み、映画を観ながら、
「これとおなじことが、たくさんの町で同時に起こっていたのだ」
という現実を考えると、現在の復興の遅れ方には憤懣やるかたない。
復興資金が使われず余っている(という言い方はおかしいが)というのも、なんとかなるだろうちょっと貸してみろ、と言いたくなる。
![遺体 明日への十日間 [DVD]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
ラストシーンは西田さんのアドリブだという。なんだよそれ。
涙無くしては観れない。
最初は、福島、宮城、岩手の沿岸の町を回り、そこでくり広げられる惨劇を目撃することになった。幼いわが子の遺体を抱きしてめて棒立ちになっている二十代の母親、海辺でちぎれた腕 を見つけて「ここに手があります!」と叫んでいるお年寄り、流された車の中に親の遺体を見つけて必死になってドアをこじ開けようとしている若い男性、傾いた松の木の枝にぶら下がっ た母親の亡骸を見つけた小学生ぐらいの少年……目に飛び込んでくるものは、怖気をふるいたくなるような死に関する光景ばかりだった。 (中略) 復興とは家庭や道路や防波堤を修復して済む話ではない。人間がそこで起きた悲劇を受け入れ、それを一生涯十字架のように背負って生きていく決意を固めてはじめて進むものなのだ。 (取材を終えて) 作品、と呼ぶにはあまりに惨い、現実を出来るだけ感傷にならないように記した、それでいて読みやすくまとめた(主題は、もちろん胸が苦しくなるほど読みづらいこと)本。 震災直後から現地に入り、現実がまだ把握出来ない状況で取材に応じた人たちの姿が客観的に描かれている。 それゆえ、地元の人たちには反発もあったという。 映画化にあたり、「なにが『遺体』だ。」と。 その気持ち、わかる。 お前らが感動するために、こんな被害を背負ってるわけじゃないんだと。 お前らの娯楽のために、ポップコーン食べながら、時間つぶしに、お手軽な感動のために、きれいな映画館でオシャレして、そんなためにわが家族は死んだんじゃないぞ、と。 「死体」と区別するための「遺体」なんて言葉、なんの意味があるんだろう。 かく言う私も、震災から10日あまりしたころ、被災地に行った。 そこかしこに「遺体安置所」と書かれた看板があり、さすがに興味本位で行くわけにはいかなかった(そんな興味、露ほどもわかなかったが)。 これ(映画化されたこの作品)を、「映画なんだから、それはそれ、これはこれでしょ」と、割り切ることが出来るだろうか。 「遺族にこそ見て欲しい」と、あなたならこれ、胸張って言えますか。 冗談じゃない。 映画じたいは、スタッフ含め現場の人たちの、製作中の心労がしのばれる。 苦しい。 西田敏行さんと志田未来さんの演技で、涙が出る。 いくらかの割合で、演技ではなかったろう。 なぜこの芝居をしなければならないのか、にもずいぶん悩まれたろう。 ひょっとして、依頼を引き受けたことにも。 それとは別に、「映画なんだから」と割り切る人らに、どうしても納得できない。 そういう、割り切れない気持ちが残る。 これを読み、映画を観ながら、 「これとおなじことが、たくさんの町で同時に起こっていたのだ」 という現実を考えると、現在の復興の遅れ方には憤懣やるかたない。 復興資金が使われず余っている(という言い方はおかしいが)というのも、なんとかなるだろうちょっと貸してみろ、と言いたくなる。

![遺体 明日への十日間 [DVD]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51ovVwwnAiL.jpg)